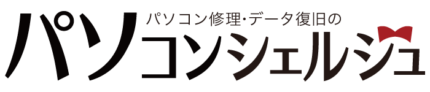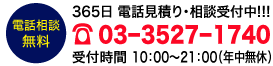パソコンが起動せず困ってしまう状況は、突然訪れることが多いものです。原因としては電源トラブルやOSの不具合、ハードウェアの故障などが考えられますが、どこが問題なのかを切り分けるのは簡単ではありません。トラブルが起きた際には、自分で対処できる範囲から点検していくことが重要です。
本記事では、パソコンが起動しないときによくある症状から基本的な対処法、さらにロゴ画面で止まる原因や黒い画面になる場合のチェックポイントなどを網羅的に解説します。メーカー別に対応方法が異なる場合もあるため、パソコンのメーカーごとに特有の対処例も合わせて紹介します。
いざというときに慌てず、正しい手順でトラブルシューティングを行えば、意外と自力で解決できるケースは少なくありません。この記事を参考に、状況に合わせた最適なアプローチを実行し、可能であれば修理費用の節約や時間の短縮につなげてください。
パソコンが起動しない時によくある症状
まずは、パソコンが起動しないときに起こる典型的な症状を把握しておくことで、原因を大まかに絞りやすくなります。
パソコンが起動しないと一口にいっても、まったく電源が入らないものから、電源ランプはつくが画面が全く映らない、といったさまざまなケースが考えられます。症状を正しく捉えることで、どの部分に問題があるのかを推測しやすくなるのがポイントです。
こうしたトラブルの原因は、電源周りの物理的故障やOSのエラー、または一時的な冷却不足や帯電など多岐にわたります。自分のパソコンの状態を落ち着いて観察し、どれに当てはまりそうかをチェックすると、次のステップの対処法を見つけやすくなります。
電源が入らない(ランプが点灯しない)
電源ボタンを押してもランプが全く点灯せず、パソコンが無反応な場合は、まず電源ユニットやACアダプタのケーブル接続の確認が最優先です。意外とコンセントやタップのスイッチが切れている、もしくはバッテリーの劣化により電力が供給されていない可能性があるため、別のコンセントやアダプタへ変えてテストすることも有効です。
またデスクトップなら電源ユニット自体の故障、ノートPCならバッテリーの過放電が関係していることもあります。ランプが点灯しない場合は、まずこれらの基礎的なチェックから始めてください。
メーカーのロゴ画面でフリーズする
パソコンの電源を入れるとメーカーのロゴが表示されるものの、そこから先に進まないケースです。BIOSやUEFI起動時のエラーや、指し込んでいるUSBデバイスの読み込み不良などが原因ということもあります。
この場合、周辺機器を外したり、BIOSの設定を初期化したりする方法が有効です。もしHDDやSSDが故障していると、OSが正常に読み込めずにロゴ画面で止まることが多いため、ストレージの状態確認も検討してください。
黒い画面のまま動かない(ブラックスクリーン)
パソコンの動作音はする、または電源ランプは点灯するにもかかわらず、モニターが真っ黒のままの場合はディスプレイやグラフィック関連の問題が考えられます。ディスプレイケーブルの接触不良やモニター自体の故障も原因になりやすいです。
また、Windowsやドライバの更新失敗によって画面出力が正常に行われなくなることもあります。別のモニターやケーブルで映像が出力されるか確認し、原因を切り分けましょう。
ブルースクリーン(青い画面)が表示される
いわゆる「ブルースクリーンエラー」は、OSやドライバの不具合、システムファイルの破損などが大きな要因です。エラーコードが表示されることが多いため、その番号を調べることで該当する不具合を特定できます。
ドライバを更新すると解決する場合もありますが、ハードウェアの故障でブルースクリーンが出るケースもゼロではありません。何度も繰り返すようなら、セーフモード環境で異常が発生するか確認すると原因をさらに絞れるでしょう。
ビープ音が鳴って起動しない
電源を入れると画面には何も表示されず、ビープ音だけが鳴る場合はパソコン内部のハードウェアにエラーが出ている兆候です。ビープ音の回数やパターンは、それぞれ意味が決まっており、マザーボード、メモリ、グラフィックカードなどの故障を示します。
エラーコード表をメーカーのサイトやマニュアルで確認し、対象部品をテストして交換または修理が必要か検討するとよいでしょう。
再起動を繰り返す・勝手に落ちる
パソコンが急に再起動を繰り返すときは、電源ユニットの不安定さやメモリエラーの他、熱暴走の疑いもあります。特にファンが動作していない、内部に埃が溜まっているなど冷却が不十分だと、負荷がかかった瞬間にシャットダウンや再起動を起こしやすくなります。
システムファイルが破損しているとOSの起動プロセスが正常に終わらず、起動ループに入ることもあります。まずは冷却や電源周りをチェックし、問題がなければOSのスタートアップ修復などを試してください。
最初に押さえておきたい基本的な対処法
パソコンが起動しないと感じたとき、すぐに焦るのではなく、まずは簡単に試せる基本的な方法を押さえておきましょう。
多くの起動不良は、意外と基本的なチェックや再接続で解決できる可能性があります。面倒ではありますが、一つひとつ手順を踏んで状況を確認することが、トラブルシューティングの大前提です。
電源ケーブルとバッテリーを確認する
電源ケーブルがしっかり挿さっているか、バッテリーが劣化していないかをチェックしましょう。ノートPCの場合は、バッテリーを取り外して電源アダプタだけで起動を試す方法も有効です。
周辺機器やディスクをすべて外す
USBメモリや外付けHDDなど余計なデバイスが原因で起動不良を引き起こす場合があります。まずはパソコン本体のみの状態にして、正常に起動できるかをチェックしてください。
パソコンを放電・冷却して再起動する
帯電によってパソコンが誤作動を起こしている場合があるため、電源を切ってコンセントを抜き、数分待ってから再度起動を試みます。熱がこもっているときは、十分に冷却してから再試行することも大切です。
電源ボタンの長押し(強制終了)で立ち上げ直す
フリーズ状態などで操作を一切受け付けなくなってしまった場合、電源ボタンを数秒間押し続けて強制的に電源を落とし、数秒後に再度立ち上げると解決するケースがあります。ただし、作業中のデータは消える可能性があるので注意してください。
メモリを挿し直す・クリーニングする
メモリの接触不良は起動不良の原因になりがちです。デスクトップPCの場合はカバーを開け、メモリをスロットから抜き差ししてほこりを除去してみましょう。ノートPCでも同様にメモリ搭載箇所へアクセスできる場合があります。
モニターケーブルの接続状態や別のケーブルを試す
黒い画面が続くときは、モニターやケーブルの不良を疑うとよいでしょう。別のケーブルや別のモニターに接続して確認できれば、どこに問題があるか明確になります。
BIOS/UEFIの設定を初期化する
BIOS設定を誤って変更してしまったり、ブートローダに問題が生じていると起動できないケースがあります。BIOSまたはUEFI上でデフォルト設定にリセットし、正しくブートできるか試してみてください。
ロゴは出るのにPCが起動しない場合の原因と解決策
メーカーのロゴ画面までは表示されるものの、OSが立ち上がらないケースでは、ブート周りやOSファイルに問題があるかもしれません。
特にWindows Updateやドライバの更新中にエラーが発生すると、ロゴ画面までは読み込まれるのにその先へ進まない、という現象が起こりやすいです。こうした場合には、回復オプションを活用するのが有効です。
OSアップデート失敗による起動不良
Windows Updateが途中で失敗すると、OSの重要ファイルが不完全なまま保存され、正常にブートできなくなることがあります。システム修復ディスクやインストールメディアがあれば、それを使って修復作業を行うことも検討してください。
セーフモードで問題を切り分ける
セーフモードで起動してみて、正常にWindowsが動作するなら、常駐アプリやドライバの不具合が疑われます。セーフモードが起動しない場合は、OSファイルそのものが破損している可能性が高くなります。
スタートアップ修復を実行する
Windowsの起動時に表示されるリカバリーオプションからスタートアップ修復を選択すると、自動的にシステムファイルの異常を検出・修正してくれる場合があります。特にブートセクタが破損しているケースなどで有効です。
システムの復元ポイントを使う
以前に作成された復元ポイントがあれば、正常に動作していた時点の状態に巻き戻すことができます。ただし復元を行うと、一部のアプリやアップデートは巻き戻る可能性があるため、その点は理解しておきましょう。
リカバリー(初期化)による対処
どうしてもOSが起動しない場合の最終手段として、工場出荷時の状態に戻すリカバリーを行う方法があります。重要なデータが消えてしまうため、事前にデータ復旧やバックアップを検討してから実施しましょう。
黒い画面で動かないときのチェックポイント
ロゴ画面が出ず、ブラックスクリーンのまま動かない場合には、ディスプレイやグラフィック出力が正常かどうかを疑ってみるとよいでしょう。
黒い画面はOSが起動しているのか、ハードウェアが動作しているのかすら分からない点が厄介です。ファンが回っているか、HDDやSSDのアクセスランプが点灯しているかなどを確認しながら、映像出力の問題かOS自体が立ち上がっていないのかを切り分ける必要があります。
グラフィックドライバのトラブルが原因の場合
グラフィックドライバの更新に失敗したり、ソフトウェア的な競合が起きると画面に何も表示されない状態になることがあります。最近ドライバに変更を加えた場合は、それを元に戻す、もしくはセーフモードで削除して再インストールを試みてください。
ケーブルやモニター自体の不具合を確認
アナログ接続やHDMIケーブルが折れているなど、物理的な損傷があると画面が真っ暗になる場合があります。別のケーブルや別のモニターを試して映像が出力されるか確認し、それでも映らない場合は本体側の故障が疑われます。
外部ディスプレイを接続して動作をチェック
ノートPCなら外部ディスプレイを接続してみれば、液晶パネルの故障かどうかを判断しやすくなります。デスクトップPCでも別のモニターを用意できるなら、グラフィックカードの不具合かモニターの不具合かを区別しやすいでしょう。
ブルースクリーン(青い画面)の原因と対処法
ブルースクリーンエラーは、主にドライバやOSの深刻な不具合が原因で発生することが多く、エラーコードを把握することが早期解決への近道です。
ブルースクリーンでは特定のエラーコードが表示され、インターネットで調べると原因や対応策がわかる場合が少なくありません。ドライバ関連の不具合だけでなく、不良セクタを含むストレージの故障が関与しているケースもあるため、ハードウェア診断ツールの使用も検討してください。
エラーメッセージ内容を調べる
ブルースクリーンにはエラーコードのほかにモジュール名やファイル名が表示されることがあります。それらを検索することで、どのドライバやシステムファイルに問題があるか特定しやすくなります。
ドライバの更新や再インストールを試す
グラフィックドライバやネットワークドライバなど、特定のドライバが原因になっている場合は、最新バージョンへ更新するか、一度アンインストールして再インストールすると解決することがあります。
メーカー別の起動トラブルへの対処例
利用しているパソコンのメーカーによって、起動時のエラーコードやリカバリー手順が異なる場合があります。代表的な事例をいくつか紹介しましょう。
メーカーによっては、起動時に独自の診断ソフトウェアが動作することもあります。またリカバリーモードへ入るキーが異なることも多いので、取扱説明書や公式サイトの情報を確認しておきましょう。
HP製PCが起動しない場合
HP独自のハードウェア診断ツールが搭載されているモデルが多く、これを利用してエラー箇所を絞り込みやすいです。リカバリーする場合はF11キーで起動するメニューを確認してみましょう。
富士通製PCが起動しない場合
富士通ではBIOS画面の中でハードウェア診断ツールを利用できることがあります。公式サイトやマニュアルでは、製品ごとの起動オプションが案内されているので、状況に合わせて利用してください。
NEC製PCが起動しない場合
NEC特有のリカバリーツールやエラーコードを参考に、どのハードウェアに問題があるのかを調べられることがあります。ユーザーズガイドのトラブルシューティング欄も要チェックです。
Dell製PCが起動しない場合
Dellはビープ音によるエラーコードの種類が細かく分かれているため、公式サイトで回数やパターンを確認し、故障個所を判別しやすいのが特徴です。部品交換の手順も詳細に案内されているので、自己修理を検討する際は参照してください。
東芝(dynabook)が起動しない場合
dynabookではF12キーなどでリカバリー起動ができるモデルが多く存在します。OSが起動しないときでも、リカバリーツールから初期化が実行できるケースがあるため、取扱説明書でキー操作をチェックしましょう。
よくある質問(FAQ)
ここでは、ユーザーから寄せられる代表的な質問と、その回答例をまとめました。
パソコンが起動しないと一言でいっても、多くの疑問や不安が浮かんできます。よくある質問をあらかじめ確認しておくと、緊急時に役立つでしょう。
Q. ビープ音が鳴るときにまず試すべきことは?
ビープ音の回数やパターンでエラーの種類が異なります。マザーボードのマニュアルや製品サイトをチェックし、メモリやグラフィックカードが正しく挿入されているか確認してください。
Q. Windows Updateの失敗でロゴ画面から進まない場合は?
セーフモードで起動して、Windows Updateの失敗した更新プログラムをアンインストールするか、スタートアップ修復やシステムの復元を行うと改善することがあります。
Q. 強制終了しても起動できないときの対処法は?
メモリや内部配線に問題がある可能性があるため、放電作業やメモリの挿し直しを試してみましょう。改善しない場合はハードウェア故障も考えられるため、メーカーサポートや修理専門業者への相談を検討してください。
Q. システムを初期化すると本当に問題を解決できる?
OSやドライバが原因の場合は初期化で解決するケースがありますが、ハードウェアが故障している場合は根治には至りません。初期化前にバックアップを取り、必要に応じて物理的な故障も疑いましょう。
Q. 修理を依頼する場合の費用や期間は?
故障しているパーツや修理内容によって異なりますが、数千円から数万円ほどかかり、修理期間も数日から数週間程度が目安です。
まとめ:トラブル時に慌てず基本対策を試し解決を目指そう
パソコンが起動しないときは、まずどのような症状かを冷静に特定し、できる範囲の基本チェックを行うことが大切です。
この記事で紹介したように、ケーブルやバッテリーなど物理的な接続から確認を始め、周辺機器の取り外し、メモリのチェック、BIOSの初期化などを試すだけで解決できるケースは意外と多くあります。それでも直らない場合は、OSの修復を試すか、一時的にセーフモードで立ち上げてドライバ不具合を切り分けるなど、段階的に対処してみてください。
もし自力では解決できず、ハードウェアの故障が疑われる際は、メーカーや修理専門店に相談するのが安心です。データ救出が必要な場合にも、早めに対応すれば復旧率が高くなる可能性があります。まずはトラブル時に焦らず、基本的な対処を順番に試して、本来のパフォーマンスを取り戻しましょう。
パソコンシェルジュでは、マックブック・surfaceなど様々な機種のパソコントラブル修理を承っております。お気軽にお問い合わせください。